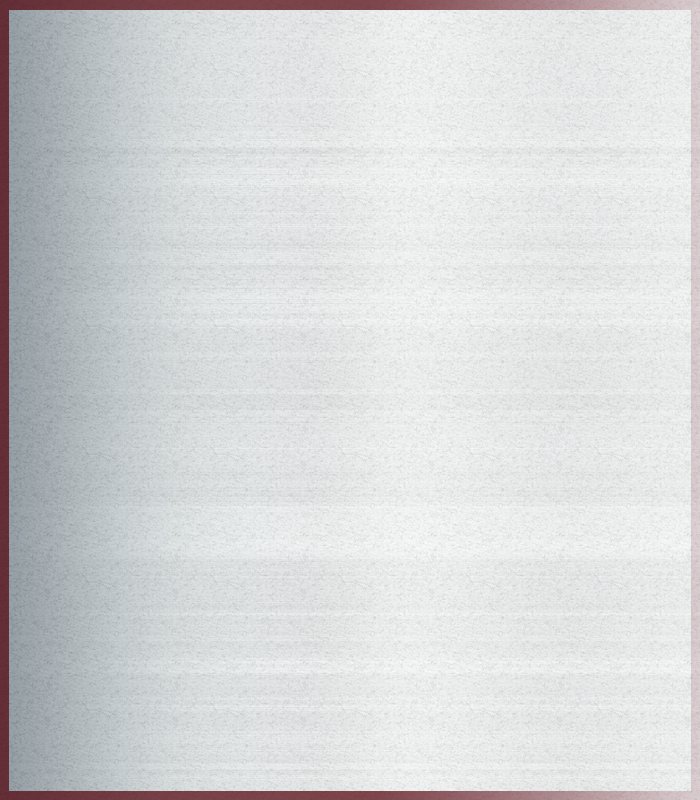
春の詩
◆世にふる 世にあって時を経る。「世」には男女関係の意もあり、「恋に人生を費やす」といった意が掛かる。
「ふる」は「降る」と掛詞で、次句へは「降る長雨」と続く。
◆ながめ じっと物思いに耽ること。「長雨」と掛詞になる。
夏の詩
◆「うの花」「うぐひす」に「憂(う)」の響きが重なる。
秋の詩
◆恋人との思い出に結びつく秋の野の風景に、袖を涙で濡らしているさまである。
冬の詩
◆「(時雨に)降り」に「古り」を、「言の葉」に「(木の)葉」を掛けている。
紹介した和歌にある掛詞や、縁語、その詩の背景を紹介します。
 平安時代 小野小町
平安時代 小野小町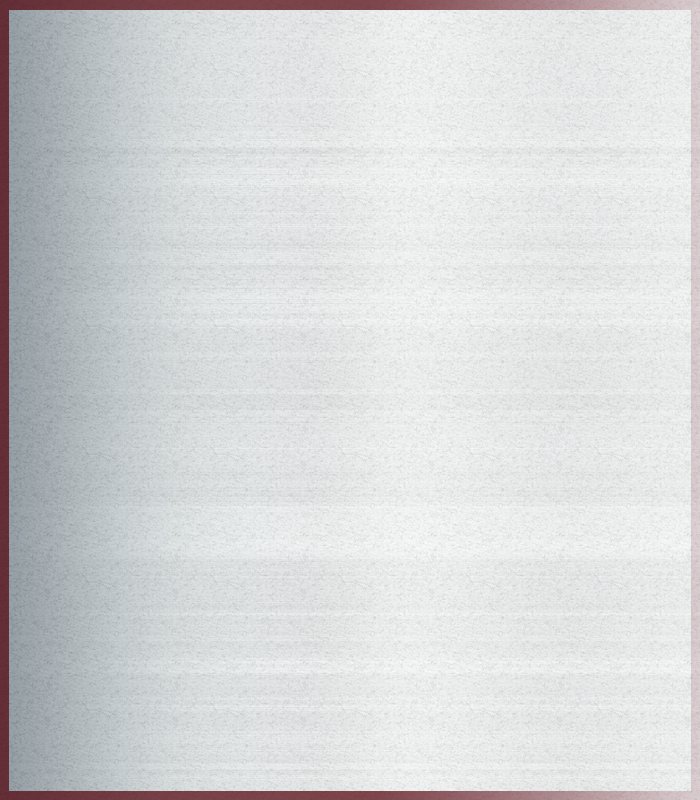
◆世にふる 世にあって時を経る。「世」には男女関係の意もあり、「恋に人生を費やす」といった意が掛かる。
「ふる」は「降る」と掛詞で、次句へは「降る長雨」と続く。
◆ながめ じっと物思いに耽ること。「長雨」と掛詞になる。
◆「うの花」「うぐひす」に「憂(う)」の響きが重なる。
◆恋人との思い出に結びつく秋の野の風景に、袖を涙で濡らしているさまである。
◆「(時雨に)降り」に「古り」を、「言の葉」に「(木の)葉」を掛けている。
 鎌倉時代 藤原定家
鎌倉時代 藤原定家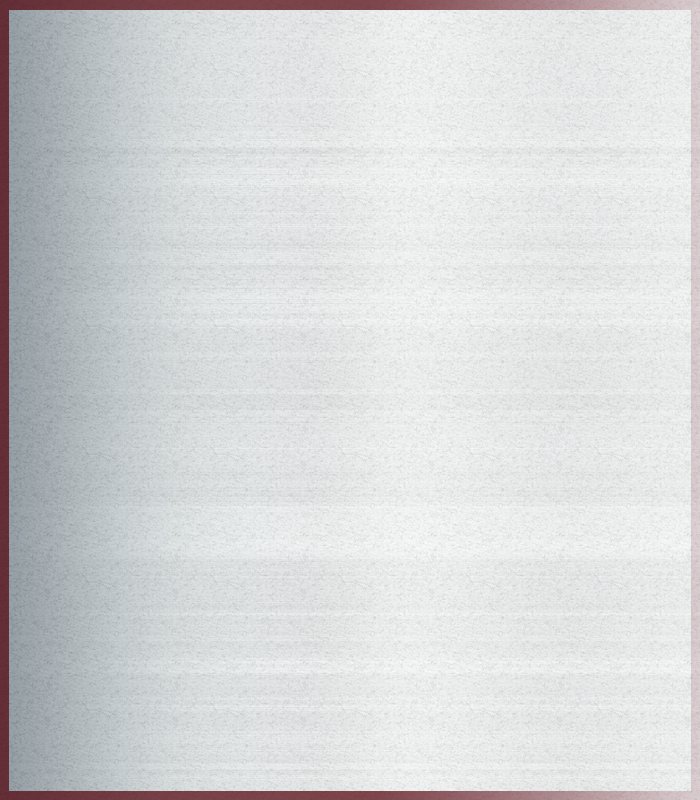
◆いくよへて「へて」は「綜へて」(経糸を整え、機に掛ける)意が掛かり糸の縁語。
◆「秋」が、秋、と、飽き、の、「こがらし」が、木枯し、と、焦がす、の、「森」が、森、と、漏り、の、それぞれ掛詞。
◆「うつろふ」は、人の心変りと木の葉の紅葉の、「露」は、露と涙の、両義で用いられ、さらに、消え、と、露、が縁語。
◆後朝、きめぎぬの別れを悲しみも、時の流れに埋もれ、真っ白な忘却にす べて包まれてゆく。
 室町時代 吉田兼好
室町時代 吉田兼好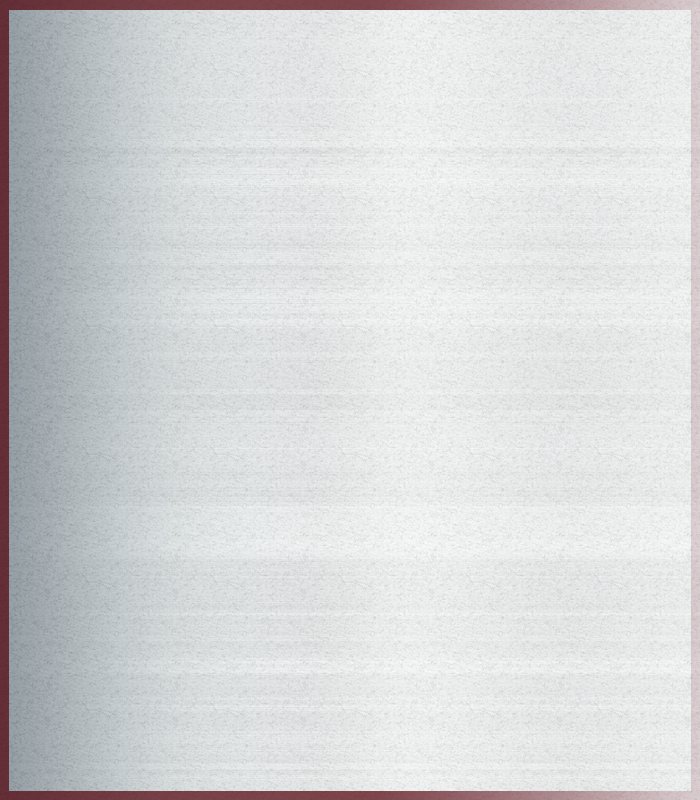
◆「御子左の中納言どの」は二条為定か。
◆「庚申」は庚申待ち。
◆網代(あじろ)は氷魚(鮎の稚魚)を獲るための仕掛け。
冬季のみ用いられ、春になれば簀をはずされて網代木(杭)のみが寂しげに立ち並ぶ。
◆柿本人麿の「もののふ八十宇治川の網代木にいさよふ浪のゆくへ知らずも」から無常の現世の暗喩ともなる。
この歌では、氷魚が寄る網代を引き合いに出して、自己の寄る辺なさを述懐している。
◆「日を」と「氷魚」が掛詞。
◆「よる」は氷魚の縁語。
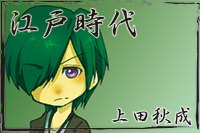 江戸時代 上田秋成
江戸時代 上田秋成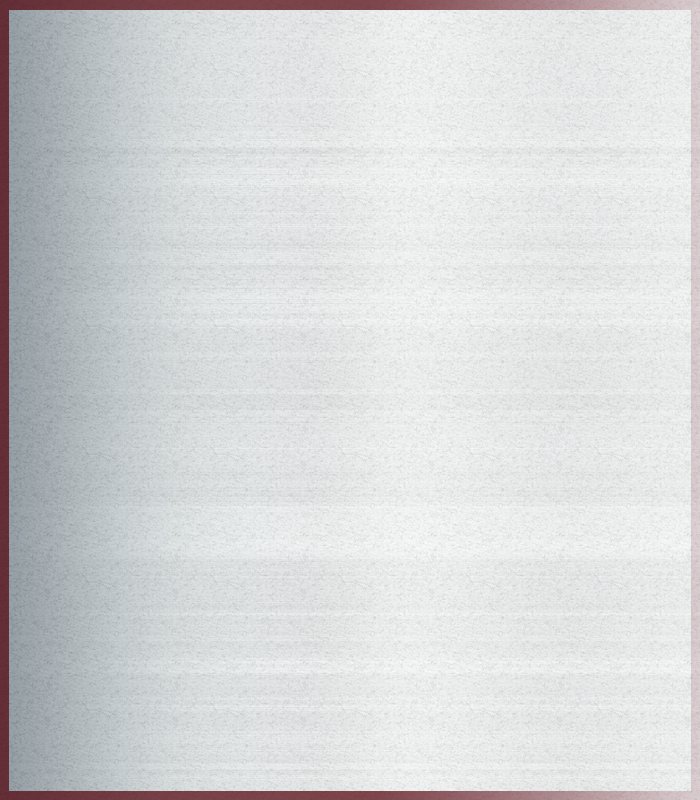
◆生駒(いこま)の山 大和・河内国境の山。
秋成が生まれ住んだ大坂からは東に眺められる。
春は東方からやって来ると考えられたので、大坂人にとっては生駒山の霞が真っ先に春を告げるものであった。
◆老けてゆく自分の顔と、毎年変わりない春霞を対比した、未曾有の立春詠。
新年の永遠回帰を春霞に象徴させて「立春霞」という伝統的な題の本意を満たしているのであるが、
何となく霞に向かって憎まれ口を叩いているようにも聞こえて面白い。
作者の独特のパーソナリティを感じさせる作である。
◆樗(あふち) 楝とも書く。栴檀のこと。
夏、香り高い薄紫の花を多数咲かせる。樹液が多いためか蝉に好まれる樹である。
<万葉集の句を巧みに応用するなど、作者の修辞の才を遺憾なく発揮している。
秋成の蝉を詠んだ歌では「鳴く蝉のやどりの松の木の本にもぬけの衣の風に吹かるる」も知られた一首。/p>
◆比良の高峰 琵琶湖の西側に聳える山々。主峰の武奈ヶ岳は標高千二百メートルを越える。
◆残る夜 明け方までの残りの夜。
◆志賀の海づら 琵琶湖の志賀あたりの湖面。志賀は琵琶湖南西岸一帯を指す古称。
◆追儺(ついな) 大晦日の夜、鬼を追い払い疫病を除くための宮中の儀式。
のち社寺や民間に広まり、近世には節分の行事となったが、この歌では宮中の年中行事を言っている。